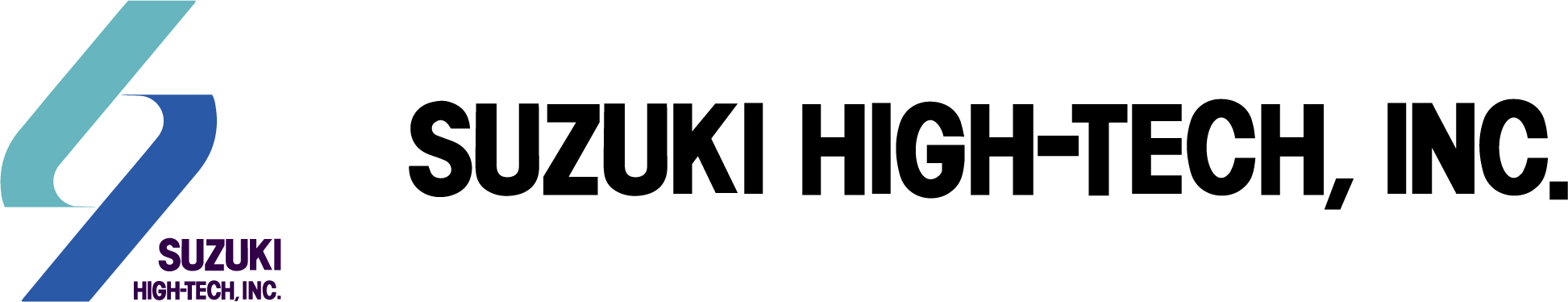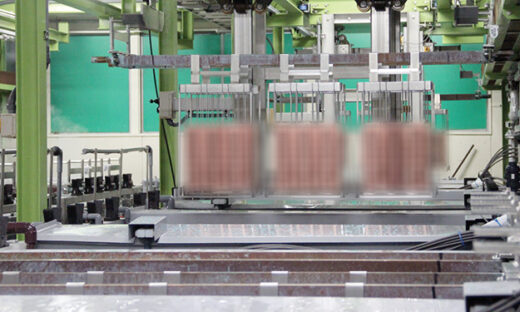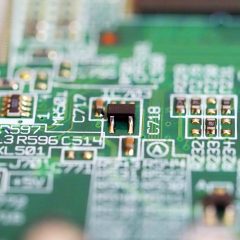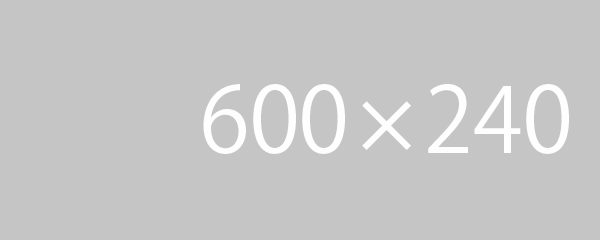無電解ニッケルめっきに錆が発生する3つの原因と対策方法を解説

無電解ニッケルめっきに錆は発生するか
無電解めっきの中でも汎用的に使われている無電解ニッケルめっきは、使用する還元剤によってニッケル-ボロン(ホウ素)や、ニッケル-リン(次亜リン酸塩)などの種類があります。
無電解ニッケルめっきの皮膜特性

このうち、無電解ニッケルめっき(中リン・高リン・ホウ素)は耐食性に優れたタイプであるため、錆びやすい素材へのコーティング(防錆)を目的に利用される場合も多くあります。無電解ニッケルめっきは錆の発生を防ぎたい製品に適しているといえるでしょう。
無電解ニッケルめっきの詳しい皮膜特性についてはこちらのコラムでもご紹介しています。ぜひご覧ください。
「錆に強い」といえる無電解ニッケルめっきですが、使用環境や処理条件によっては錆びてしまう可能性があります。
このコラムでは、無電解ニッケルめっきで錆が発生する主な原因や、錆のリスクを抑えるための対策についてスズキハイテックがご紹介します。
無電解ニッケルめっきに錆が発生する3つの原因
前述したように、無電解ニッケルめっきは耐食性に優れたタイプであれば、基本的には錆びにくいめっき皮膜ですが、それでも条件によって錆が発生する可能性はあります。
めっき品に錆が発生した場合、さまざまな原因が考えられます。その中でも代表的な原因として、以下の3つが挙げられます。
【無電解ニッケルめっきが錆びる原因】
1.使用環境(薬品、高温多湿な環境)
2.めっき不良
3.ピンホール(孔食)
それぞれの原因について詳しくご紹介しましょう。
錆の発生原因(1)使用環境(薬品、高温多湿な環境)
使用環境によっては皮膜の耐食性が活かされず、錆びる場合があります。
無電解ニッケルめっきが苦手とする環境として、以下が挙げられます。
- 高温多湿な環境
- 薬品にさらされる環境
高温多湿な環境下で長期間使用または保管をすると、時間の経過とともに皮膜が劣化し、錆びる場合があります。そのため、気温(室温)や湿度が管理された環境下で保管および使用されることをおすすめします。
また、無電解ニッケルめっきは耐薬品性にも優れていますが、一方で苦手とする薬品(塩酸や硝酸、アンモニア水、漂白剤など)もあり、そのような薬品にさらされる環境では、めっき皮膜が変化し、錆びてしまうことがあります。
錆の発生原因(2)めっき不良
ふたつめに考えられる錆の原因は「めっき不良」です。
めっきに前に行われる前処理に不備があると、めっきの密着不良が起こり、局所的に錆びる可能性があります。例えば、基材の表面に切粉や油分などが残留していた場合、剥離や膨れなどの不良が発生し、結果として錆が発生する場合があります。
また、前処理工程に問題がなくても、めっき処理の段階でめっき浴に不純物が混入していると、めっき皮膜に欠陥が生じる可能性があり、無めっき部分やピンホールが発生し錆が発生する原因となり得ます。
錆が発生した場合には処理工程の履歴を確認し、前処理が適切に実施されていたか、また薬剤や洗浄に問題がなかったかを検証し、原因の特定や究明を行います。
錆の発生原因(3)ピンホール(孔食)
ピンホールとは、めっき皮膜に発生する「穴」のことです。非常に小さな穴なので、肉眼で見ることはできません。
ピンホールがあると、基材の表面(素地)が一部露出している状態となるため、大気中の酸素や水と素地が触れ、素地から錆びてしまう可能性があります。また、錆だけでなく、導電性など機能の低下の原因になる場合もあります。
ピンホールが発生する原因は複数ありますが、「水素ガスの発生」が代表的な原因として挙げられます。
めっき処理中に発生した水素ガスが基材の表面に留まると、この水素ガスを避けるように金属皮膜が形成されるため、水素ガスが留まっていた部分にはめっきがついていない「無めっき」の状態になるのです。
できる限り防ぎたい存在ですが、ピンホールの完全な予防は困難とされています。
ピンホールによる錆の対策としては、めっき皮膜の厚付けや多層などの工夫のほか、防錆を目的とした後処理の実施が挙げられます。
無電解ニッケルめっきの錆の発生を防ぐ対策
これまで、耐食性に優れた無電解ニッケルめっきでも、錆が発生する可能性はあり、代表的な原因についてご紹介しました。
錆は製品の耐久性や機能に影響を及ぼすため、製品の信頼性の低下に繋がります。また、装飾品の場合も、美観を損なう可能性があるため、製品の価値への深刻な影響が懸念されます。このようなリスクを防ぐためにも、無電解ニッケルめっきの錆対策や対処は重要といえるでしょう。
ここでは、無電解ニッケルめっきの錆対策についてご紹介します。
めっきプロセス(前処理、めっき処理、後処理)の見直し
無電解ニッケルめっきを施した製品に錆が発生した場合は、製品をSEMなどで分析をし、原因を突き止めます。
分析の結果、めっき不良によるものである場合は、原因に応じためっきプロセスの見直しを行う必要があります。
(前処理の見直し(スマットの除去や洗浄など)、めっき液の不純物であれば濾過の実施など)
前処理は素材に適した方法にて行う必要があるため、素材への知識は重要です。
当社、スズキハイテックは長年さまざまな素材にめっき処理を行ってきた実績がありますので、幅広い素材の知識、まためっきのノウハウがございます。
めっきの品質で課題がありましたらお気軽にご相談ください。
めっき皮膜を厚くつける
ピンホールによる錆を防ぐためには、めっきの膜厚を厚くすることも対策のひとつです。
めっきの膜厚に厚みをつけると、ピンホールの発生を防げるため、錆対策に有効であるといえます。
また、厚付けの他にも、無電解ニッケルめっきだけ(単層めっき)ではなく、多層めっきにすることも有効な手段です。
※ただし、寸法精度が厳しく求められる製品においては、膜厚が寸法公差に影響を与える場合があるため、厚付けを検討する場合には注意が必要です。
最適な環境での使用や防錆処理をする
無電解ニッケルめっきは通常錆びにくい皮膜ですが、高温多湿な環境、また酸性の環境下では皮膜が劣化し、錆びる場合があります。
そのため、無電解ニッケルめっきの性能を長期間維持するには、高温多湿の環境、また薬品が飛散している環境を避け、できるだけ安定した環境下での使用や保管が重要です。
過酷な環境下での使用が見込まれる場合には、最上層にクロムめっきなど耐久性の高いめっきを重ねるほか、無電解ニッケルめっき後の防錆処理(後処理)を検討するのもひとつの方法です。
めっきの防錆(耐食性)の課題はスズキハイテックにお任せください
無電解ニッケルめっきは、通常優れた耐食性を持っているため、錆に強いタイプのめっきではありますが、使用条件によっては錆びる場合があります。
今回のコラムでは、錆が発生する原因や、その対策方法について詳しくご紹介してきました。
スズキハイテックは無電解ニッケルめっきに対応しており、自動車部品や電子機器をはじめとする精密部品へのめっき実績が豊富にあります。長年培ってきたノウハウ、そして最新の設備にて高品質なめっき技術を提供いたします。

「防錆のはずなのに錆びてしまった」
「処理条件を見直すべき?」
このようなことでお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
めっきのプロが丁寧にお伺いし、素材に最適なめっきプロセスをご提案いたします。
お問い合わせ先はこちら
電話番号:023-631-4703
お問い合わせフォーム